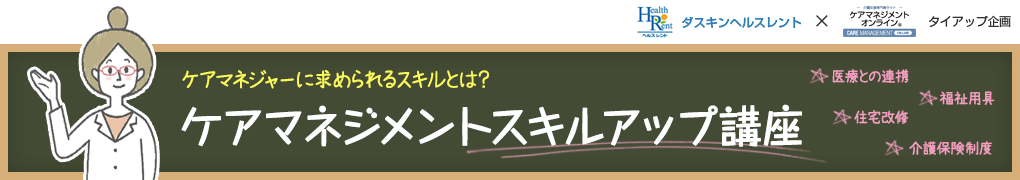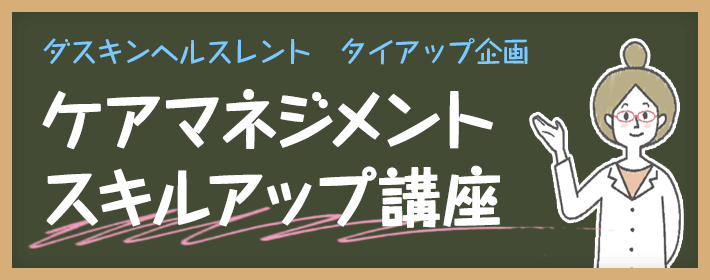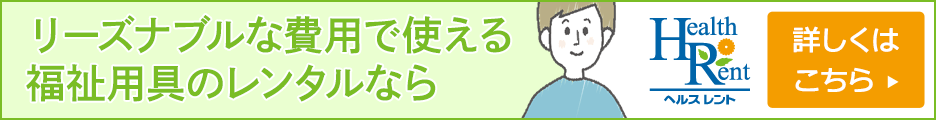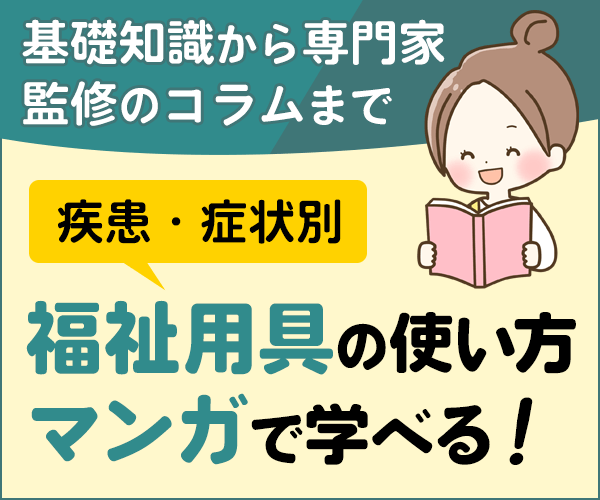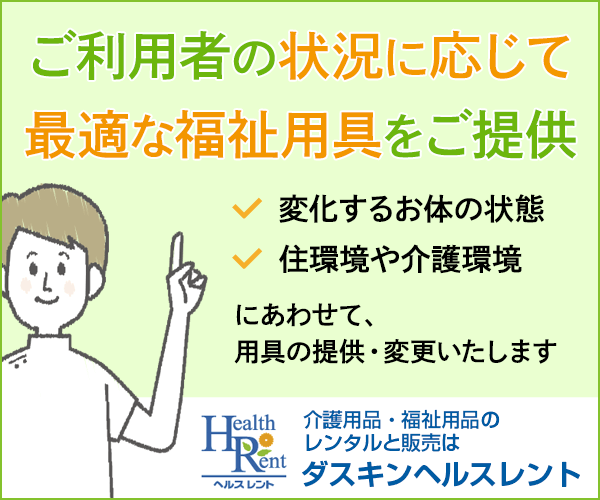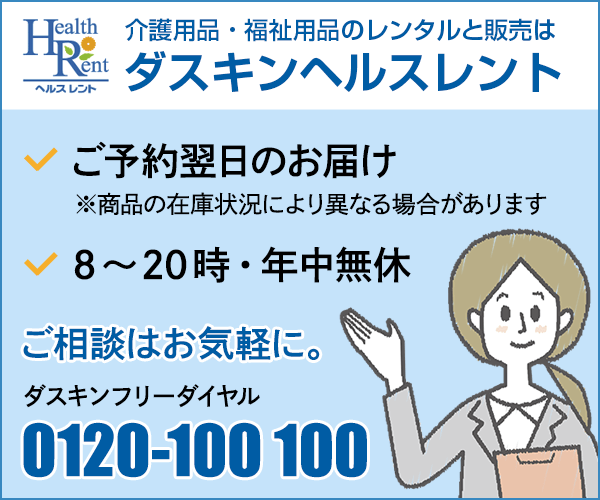白木裕子の「実践! 仕事力の磨き方」 VOL.29
激変必至の24改定、ケアマネが押さえておきたいこと(後編)

日本ケアマネジメント学会副理事の白木裕子先生が、介護保険制度や社会情勢に対応するためのポイントや心構えを、わかりやすく伝授する「実践! 仕事力の磨き方」。第29回は2024年度に予定される介護報酬改定(24改定)に向けた議論の中でも、ケアマネジャーが押さえておきたいポイントを紹介します。
「新サービス」「福祉用具×プラン検証」「包括と居宅の役割分担」に注目!
前回の記事では24改定でケアマネジャーが押さえておきたいポイントとして、次の3点を挙げた上で、「新サービスの各種基準」に関し、具体的に把握しておきたい内容について紹介しました。
- (1)新サービス(デイサービス+訪問介護)の各種基準
- (2)福祉用具に関する、新たなケアプラン検証の具体的内容
- (3)地域包括支援センターと居宅介護支援の新たな役割分担
今回は「福祉用具に関する、新たなケアプラン検証の具体的内容」と「地域包括支援センターと居宅介護支援の新たな役割分担」の具体的な注目点について触れたいと思います。
具体像が見えない「福祉用具×ケアプラン検証」…備えるべきことは?
まずは、「福祉用具に関する、新たなケアプラン検証」について。これは昨年の国の検討会で「手すりなど、同じ種類の福祉用具を数多く位置付けているケアプランは、地域ケア会議で検証すべきではないか」という意見が出たことを踏まえたものです。この案に関する具体的な議論も、介護給付費分科会で行われるでしょう。
ならば「福祉用具に関する、新たなケアプラン検証」は、どんな仕組みになるか―。残念ながら、現段階ではまったくわかりません。
できれば「定められた基準数を超えた場合、その理由や背景をケアマネが保険者に届け出る。保険者は、届け出の内容について、第三者の視点も交えて検証する」といった仕組みだとありがたいですね。生活援助のように基準数を超えただけで、地域ケア会議で検証される仕組みだと、居宅介護支援の現場にとって負担が大きすぎます。
それでも生活援助と同じような仕組みが導入される可能性はあります。ですので、現場のケアマネジャーは、同じ種類の福祉用具を数多くケアプランに位置付けた場合は、なぜ、そうした対応が必要だったのかを説明できるようにしておいたほうがよいでしょう。
居宅も要支援を直接担当可能に―注目は介護予防支援の単位数!
「地域包括支援センターと居宅介護支援の新たな役割分担」については、2024年度から要支援者を居宅介護支援事業所が直接担当できるようになる見通しです。地域包括支援センターの業務負担を軽くするための施策ですが、現在の委託方式に比べれば、居宅介護支援事業所も負担軽減につながるでしょう。
ただ、介護予防支援の単位数が今と同じでは、要支援者を担当しようという居宅介護支援事業所は増えません。制度変更にあわせて介護予防支援の単位数がどこまで引き上げられるのか―。これも介護給付費分科会の議論の注目点です。
なお、居宅介護支援事業所が要支援者を直接担当できるようになる前に「これまで地域包括支援センターだけが要支援者を直接担当してきたことで、利用者には、どのような効果があったのか」ということは、はっきりさせてほしいですね。この点がわからないまま制度だけを変えても、決して良い結果を生まないでしょうから。
そのほか、24改定にあわせて、居宅介護支援事業所を地域包括支援センターのサブブランチ(窓口)やサブセンターとして活用する方針も示されていますが、その業務範囲や人員配置、報酬などについても、介護給付費分科会で議論される見通しです。
- 白木 裕子 氏のご紹介
-
 株式会社フジケア社長。介護保険開始当初からケアマネジャーとして活躍。2006年、株式会社フジケアに副社長兼事業部長として入社し、実質的な責任者として居宅サービスから有料老人ホームの運営まで様々な高齢者介護事業を手がけてきた。また、北九州市近隣のケアマネジャーの連絡会「ケアマネット21」会長や一般社団法人日本ケアマネジメント学会副理事長として、後進のケアマネジャー育成にも注力している。著書に『ケアマネジャー実践マニュアル(ケアマネジャー@ワーク)』など。
株式会社フジケア社長。介護保険開始当初からケアマネジャーとして活躍。2006年、株式会社フジケアに副社長兼事業部長として入社し、実質的な責任者として居宅サービスから有料老人ホームの運営まで様々な高齢者介護事業を手がけてきた。また、北九州市近隣のケアマネジャーの連絡会「ケアマネット21」会長や一般社団法人日本ケアマネジメント学会副理事長として、後進のケアマネジャー育成にも注力している。著書に『ケアマネジャー実践マニュアル(ケアマネジャー@ワーク)』など。
関連記事
会員限定コンテンツのご案内

CMO会員限定コンテンツの「CMOたより」は、ケアマネジャーのみなさまの業務に役立つ情報を配信しています。メッセージは定期的に届きますので、ぜひログインして最新メッセージをごらんください。
※会員限定コンテンツのため、会員登録が必要です。
- ダスキンからはこんな「たより」をお届けしています
- 福祉用具に関するお役立ち情報
- 福祉用具専門相談員が語る、ご利用者様とのエピソード
- ケアマネからの福祉用具に関する疑問・質問に回答