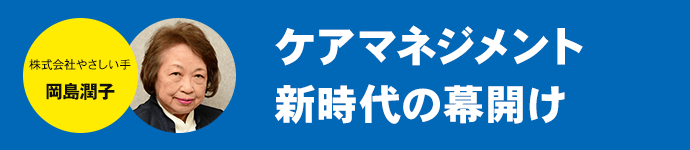
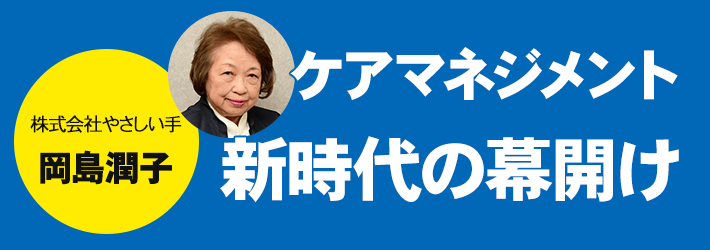
ケアマネジメント新時代の幕開け
定期巡回と複合型の創設 在宅生活の継続に光を見た
- 2022/10/27 09:00 配信
- ケアマネジメント新時代の幕開け
- 岡島潤子
-


今回は、2012年(平成24年)の制度改正と介護報酬改定について見ていきましょう。
私はこの改正・改定に関しては、介護保険部会も介護給付費分科会も、ほとんど毎回傍聴しました。
それは、2012年が診療報酬との同時改定だったこと、将来に向けた国づくり・仕組みづくりの議論が多くなされていたこと、そして何よりも大きな理由は、戦後の発展を支えてきた団塊の世代が、2015年には65歳を迎えるという大きな転換期を間近に控え、その対応のための基盤づくり、準備の大事な時期だったからです。
2012年の制度改正と介護報酬改定は、第5期(2012年~14年)の介護保険事業(支援)計画に向けたものですが、団塊の世代が75歳を迎える2025年(第9期)までを見据えたものでした。同年までに地域包括ケアシステムを構築し、高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごせる地域づくりを進めることが、国の中長期の目
……

- 岡島潤子
- 慶応義塾大学文学部卒業(社会学専攻)。1999年に介護支援専門員の資格を取得後、同年9月に株式会社やさしい手に入職。新宿区で居宅介護支援事業所の立ち上げなどに携わった後、2005年7月に同社初の居宅介護支援事業部を創設。現在は同社経営企画部の顧問として、総勢383人のケアマネジャーをスーパーバイズしている。厚労省をはじめとする国の委員会の委員のほか、日本ケアマネジメント学会の代議員や一般社団法人「東京ケアマネジャー実践塾」の理事長など、ケアマネの関連団体で多数の要職を務めている。主任介護支援専門員、社会福祉士。
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。




