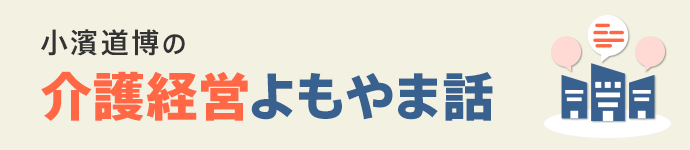
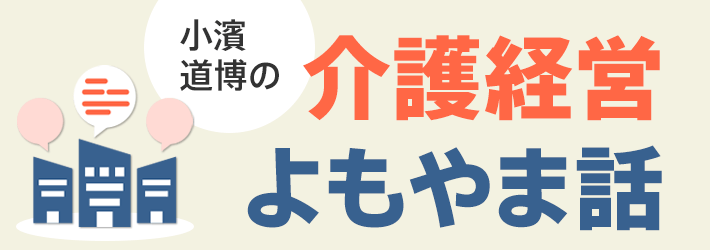
小濱道博の介護経営よもやま話
本格的に始まった運営指導、居宅介護支援の注意点
- 2024/06/28 09:00 配信
- 小濱道博の介護経営よもやま話
- 小濱道博
-


今年度の介護報酬改定は、過去最大規模の改定となった。それは、変更された項目の数が過去最多という意味でもある。人員基準、運営基準はもとより、既存の加算の多くに算定要件の変更があった。
新型コロナの感染法上の分類が季節性インフルエンザと同じ5類へ移行した昨年度から、行政の指導件数が急増している。
毎年6月は、新年度の運営指導が本格的にスタートする月である。今回は、居宅介護支援事業所が特に注意すべき運営指導におけるポイントを見ていく。
前回の介護報酬改定の内容の再確認を!
今年度の運営指導では、令和3年度(2021年度)の介護報酬改定の内容が重点的に確認されるであろう。同年度はコロナ禍の真っただ中だった。今一度、漏れがないかどうか確認してほしい。
1. 限度額の利用割合でケアプラン提出
……

- 小濱道博
- 小濱介護経営事務所代表。株式会社ベストワン取締役。北海道札幌市出身。全国で介護事業の経営支援、コンプライアンス支援を手掛ける。介護経営セミナーの講師実績は、北海道から沖縄まで全国で年間250件以上。個別相談、個別指導も全国で実施。全国の介護保険課、介護関連の各協会、社会福祉協議会、介護労働安定センター等主催の講演会での講師実績も多数。C-MAS介護事業経営研究会・最高顧問、CS-SR一般社団法人医療介護経営研究会専務理事なども兼ねる。
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。




