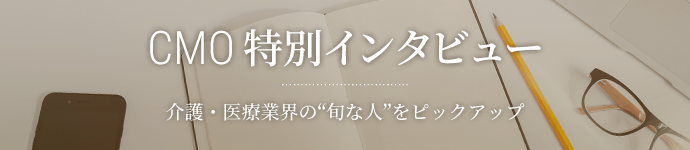
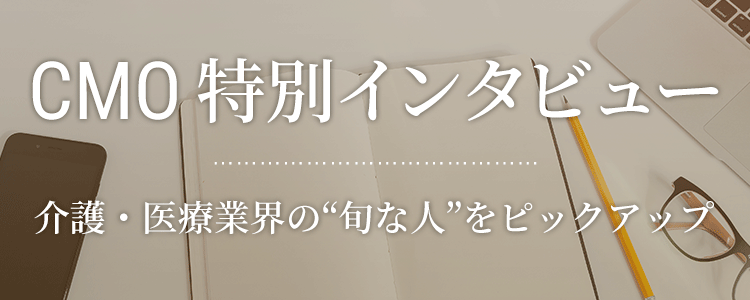
CMO特別インタビュー
日本一の介護プレゼンター決定 群馬で大会主催 /髙橋将弘(日本介護福祉魅力研究協会・代表理事)
- 2022/11/10 09:00 配信
- CMO特別インタビュー
-


介護福祉の仕事のやりがいを発信できる人を増やし、離職防止や業界全体のイメージアアップにつなげたい―。こうした思いから、今年4月、同じ志を持つ仲間3人と共に、一般社団法人日本介護福祉魅力研究協会を設立した。今月11日の「介護の日」には、クラウドファンディングで集めた資金を元に、介護のプレゼンター日本一を決める「第1回ベスト介護JAPAN」を群馬県前橋市内で開催。当日の模様はインターネットでライブ配信される予定だ。同協会発足の背景などについて、髙橋将弘代表理事に聞いた。
―日本介護福祉魅力研究協会を立ち上げた経緯を教えてください。
介護福祉の業界には、一般的にいわゆる「3K」に代表されるマイナスなイメージが強くありますし、高齢者の虐待や認知症の方の交通事故といったネガティブなニュースばかりクローズアップされがちです。
しかし、厚生労働省の発表を見ると、介護現場で働く人
……
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。




