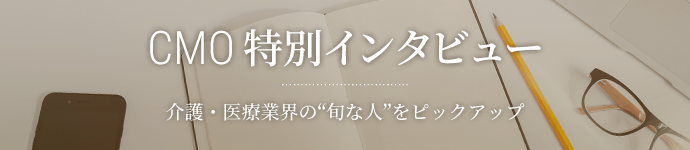
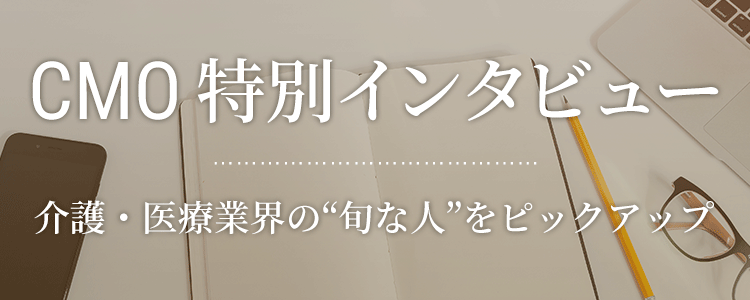
CMO特別インタビュー
「主マネは優秀か」発言の真意とは? /武久洋三(医師、ケアマネジャー)【後編】
- 2022/08/15 09:00 配信
- CMO特別インタビュー
-


介護報酬の改定案をまとめる社会保障審議会介護給付費分科会で、およそ13年半にわたり、日本慢性期医療協会(日慢協)の代表として委員を務めた武久洋三さん。歯に衣着せぬ物言いで知られるだけに、その発言は時に物議を醸すこともあった。主任ケアマネジャーの管理者要件について議論が行われた際は、「主任ケアマネは優秀なのか」と指摘し、研修の質を問題視した。その後、発言を撤回して謝罪したが、その真意は一体どこにあったのか―。武久さんに直撃した。
―介護給付費分科会で主任ケアマネの管理者要件について議論が行われた際、「主任ケアマネは優秀なのか」と発言したことがありました。その後、発言を撤回されましたが、その真意はどこにあったのですか。
“1人ケアマネ”の存在を否定することが、厚生労働省の方針なのです。主任ケアマネの管理者要件は、そう受け取らざるを得ない制度の見直しだったと思います。
主任
……
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。




