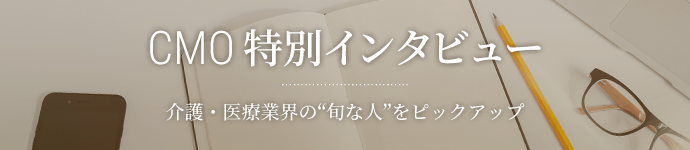
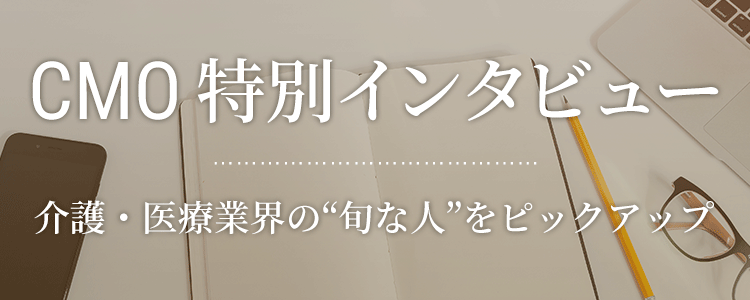
CMO特別インタビュー
一体なぜ?ケアマネが市長に転身した理由 /松本哲治(沖縄・浦添市長)【後編】
- 2022/07/12 09:00 配信
- CMO特別インタビュー
-


「良いケアマネは良い政治家になれる」―。ケアマネジャー出身の松本哲治市長の持論だ。そもそも、松本市長はなぜ、政治の道へ進んだのか。ケアマネと政治家の共通点とは―。インタビュー後編では、行政の当事者としてかじ取りする際の苦労にまで話は及んだ。
―ケアマネから一転、政治の道を志したのは、何かきっかけがあったのですか。
特別支援学校に通う子どもの支援をしていた時、送迎のことで行政ともめたことがありました。車椅子の女の子が小学校に進学する際、「みんなと同じ学校に行きたい」と言っているのに、学校側は「エレベーターを含めてバリアフリーじゃないと受け入れられない」と断ってきたんです。とにかくルールがガチガチで、教育委員会に行ったり、学校の先生を交えて会議をやったりしたんですが、一向にらちが明かない。
これはたくさんある中の一つの例です。「これは決まりですから」とか、「この子だけ
……
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。




