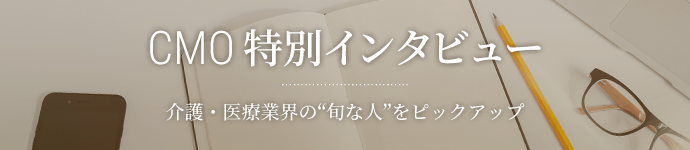
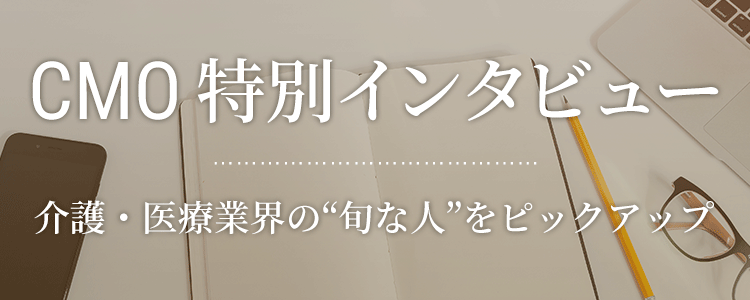
CMO特別インタビュー
※この記事は 2021年9月8日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
お笑い修行でケアマネジメント業務に変化も?!/小林彰宏(ケアマネジャー、芸人)【後編】
- 2021/09/08 09:00 配信
- CMO特別インタビュー
-


1年半に及んだお笑い修行を終え、地元・静岡に戻った小林彰宏さんは、「モニタリングに行った時、『利用者さんを笑顔にさせたい』という気持ちがわいてくるようになりました」と話す。他の介護サービス事業者と接する際も、「お笑いをベースとした明るい対応をするようになった」ことで来訪者が増えたという。笑いでケアマネジメント業務は変わるのか―。オンラインインタビューの後編では、お笑い修行の成果や今後の目標などについて聞いた。
小林さんは「ショーレースにも出たい」と意欲を語る(ご本人提供)
目指すは「オンリーワンの介護芸人」
―1年半の学校生活を終えて、どのようなことを感じましたか。
とにかく、お笑いは難しいというのが、正直なところです。人を笑わせるためには、すごく難しい技術が必要だということを痛感しましたね。笑わせるためには、ちゃんとしたロジックがあるんだな、と。
……
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。




