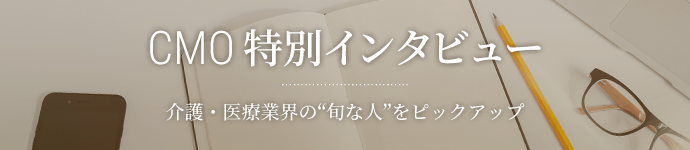
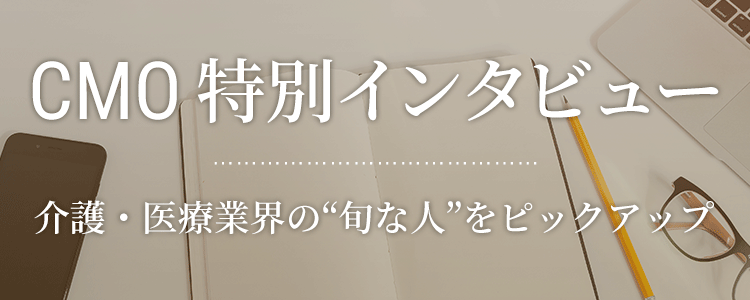
CMO特別インタビュー
※この記事は 2020年3月9日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
ケアマネは「代理人」の原点に戻れ!/三原岳(ニッセイ基礎研究所・主任研究員)
- 2020/03/09 09:00 配信
- CMO特別インタビュー
-


「ケアマネ 独立性の確保急げ」―。ケアプラン有料化の議論が大詰めを迎えていた昨年11月、日本経済新聞に掲載された寄稿が、ケアマネジャー界隈で話題となった。寄稿者は、ニッセイ基礎研究所の三原岳主任研究員。同紙上では、ケアプランに介護保険サービスを組み込まないと報酬が支払われない制度の問題を指摘し、ケアマネの独立性を確保する方策の一つとして、居宅介護支援費を保険給付から切り離すことを提案している。この大胆なアイデアの真意について、三原氏に聞いた。
―日経新聞の寄稿で伝えたかったことを、改めて教えてください。
介護保険制度の創設時、ケアマネには利用者の「代弁機能」「代理人機能」が期待されていました。それは介護保険サービスに限らず、ソーシャルサービスも含め、利用者の生活を幅広く支えるということです。それが当時の国の考え方でしたし、国会答弁にも残っています。しかし、実態は
……
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。




