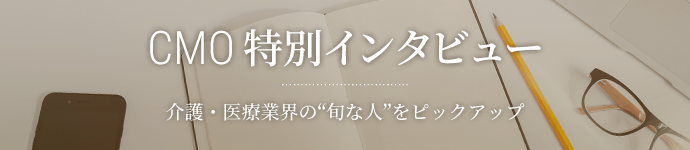
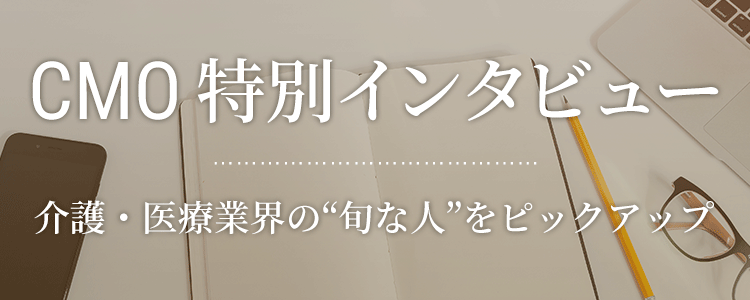
CMO特別インタビュー
※この記事は 2019年7月19日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
ナースこそ、同じ目的を持ったケアマネの仲間/齋藤訓子(日本看護協会副会長)
- 2019/07/19 09:00 配信
- CMO特別インタビュー
-


「『どうしてもっと早く連絡しないのか』『なぜ放っておいたのか』など、相談者を責める対応はしない」「ケアマネジャーへの相談業務に携わる訪問看護師は、ケアマネジャーの資格を持つ人や、相談員などの研修受講者が望ましい」-。いずれも、日本看護協会が厚生労働省の調査研究事業で取りまとめた訪問看護師向けのガイドラインに盛り込まれた心得だ。医療が必要な利用者を抱えるケアマネを訪問看護師が支援するために作られたこのガイドラインには、ケアマネを理解し、その業務に配慮した上で、連携を促す内容がたっぷり記載されている。検討委員会の委員長を担った日本看護協会の齋藤訓子副会長は「ナースこそが、目的を共有するケアマネの仲間」とし、その連携の必要性を力説する。齋藤副会長にガイドラインを作った狙いなどを聞いた。
―ガイドラインの正式名称は「医療ニーズを有する利用者のケアマネジメントに関する看護師によ
……
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。




