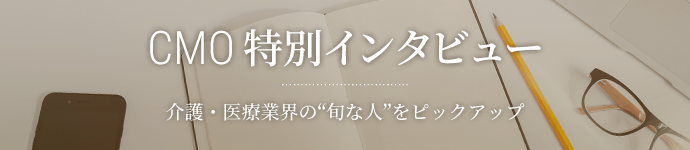
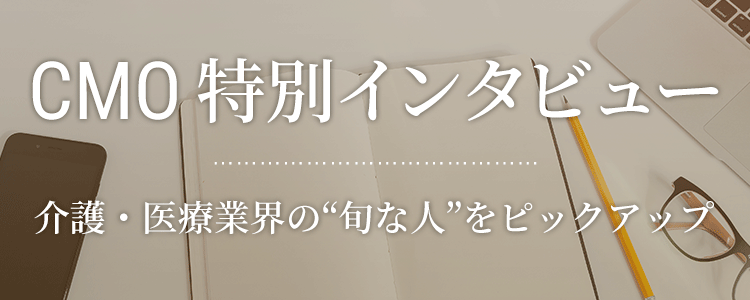
CMO特別インタビュー
※この記事は 2019年3月4日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
利用者数の“上限”、5年後には撤廃を/高橋泰(国際医療福祉大 赤坂心理・医療福祉マネジメント学部長)【後編】
- 2019/03/04 09:00 配信
- CMO特別インタビュー
-


現在、ケアマネジャー1人が担当できる利用者の数は、35人が事実上の上限となっている。高橋氏は、こうした業務上の制約が、介護の効率性を高めるICTやAI(人工知能)などを普及させる上での最大の障害だとし、サービスの質が低下しないことが実証できた場合は、現行の基準を撤廃し、1人のケアマネが担当できる利用者の数を増やす必要があると指摘する。「5年後にはそうならないと、2025年以降のさらなる高齢化には対応できない」―。高橋氏はこう警鐘を鳴らす。
―AIの進化によって、いわゆる「ケアマネ不要論」が再燃するとの見方もありますが、これについてはいかがでしょう。
ケアマネの仕事は、ケアプラン作成とケアのコーディネーションに分けることができます。そして、現在AIができるのは、ケアプラン作成の支援です。AIは、高齢者が今後どのようになるかを予測する能力に優れているので、国
……
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。




