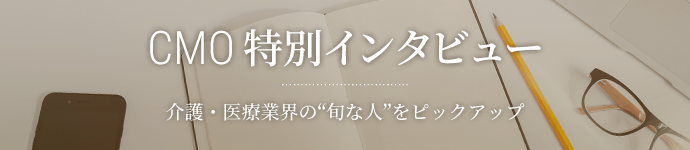
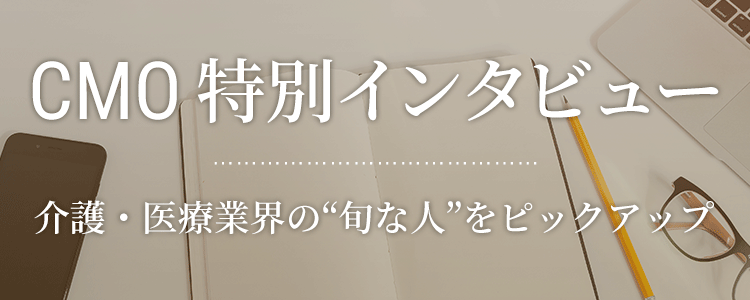
CMO特別インタビュー
※この記事は 2018年12月6日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
ケアマネ×牧師、“二刀流”が考える死生観とは?/佐々木炎(NPO法人 ホッとスペース中原 代表)【後編】
- 2018/12/06 09:00 配信
- CMO特別インタビュー
-


この春の制度改正では、「共生型」という新たなサービス類型がつくられた。今後、65歳を迎える障がい者が増えることが予想される中、一つの事業所でサービスを受けやすいようにすることで、障がい者が住み慣れた地域で暮らし続けることが狙いだ。「ケアマネは地域共生社会のハブ、つなぎ役になるべきだ」。NPO法人「ホッとスペース中原」の佐々木炎代表はこう主張する。ケアマネジャーと牧師、“二刀流”の宗教者が考える死生観とは―。
―佐々木さんはどのような経緯で牧師になられたのですか。
牧師になったのは26歳の時です。もともと、私は「妾(めかけ)」の子どもでした。今で言う「非嫡出子」(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子供)です。精神疾患を抱えた父は仕事ができず、私は貧しさの中で、非行に走りました。父親から虐待を受けていたため、同じように暴力で人を押さえ付ける、支配するとい
……
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。




