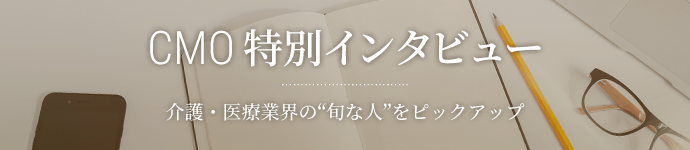
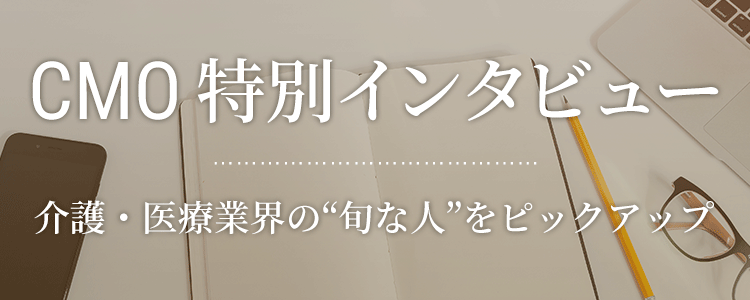
CMO特別インタビュー
※この記事は 2018年8月6日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
主任ケアマネ=管理者で、事業所統合が進む可能性も/田中滋(埼玉県立大理事長、慶大大学院名誉教授)【後編】
- 2018/08/06 09:00 配信
- CMO特別インタビュー
-


4月の介護報酬改定では、居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限定するという、大きな制度改正が導入された。その制度改正が持つ意味は何か―。前編に引き続き、田中滋・埼玉県立大理事長に話を聞いた。
―3年後には、居宅介護支援事務所の管理者が、主任ケアマネに限定されることになります。1人で運営するケアマネの中には、主任ケアマネの資格を取るめどがなく、3年後には事務所を畳まなければならないかと悩む人も多くいるようです。実際、3年後、主任ケアマネを確保できず運営できなくなる事業所が出てくる可能性はあるでしょうか。
ありえるでしょう、それは。ただし、ケアマネジメントに対する需要と重要性は今後も変わりません。例えば「10カ所の事業所で40人のケアマネがいる」状態が、3年後には「6カ所の事業所で40人のケアマネがいる」となる集約化は、当然想定されます。
……
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。




