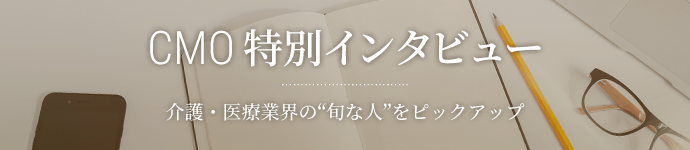
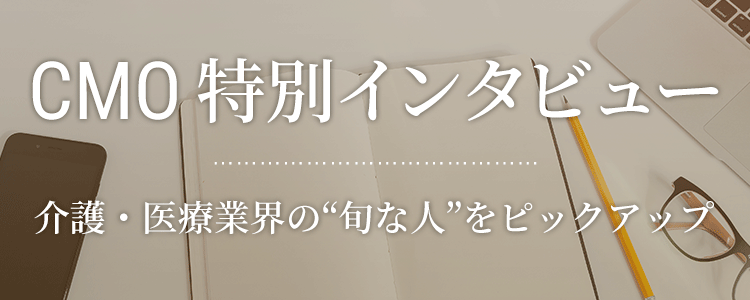
CMO特別インタビュー
※この記事は 2018年6月29日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
「利用者意識」育てるケアマネになって/島村八重子(全国マイケアプラン・ネットワーク 代表)
- 2018/06/29 09:00 配信
- CMO特別インタビュー
-


「全国マイケアプラン・ネットワーク」は、自らケアプランを作成する要介護者や家族、賛同者ら230人ほどでつくる市民団体だ。ケアマネジャーに任せっきりにするのではなく、わが事として介護を考える―。団体名には、こうした思いが込められている。メンバーには、約50人のケアマネも賛同者として名を連ねるという。ケアプラン有料化の議論が再燃する中、ケアマネと利用者の関係性はどうあるべきなのか。島村八重子代表に話を聞いた。
―全国マイケアプラン・ネットワークは、どのような経緯で発足したのでしょうか。
私たちは2001年9月に立ち上がった市民団体です。設立した理由は、要介護者や家族がケアプランを自己作成するための環境づくりでした。当時、まだ介護保険制度が始まったばかりで、情報も少なかったため、ケアプランを自分で作成していた利用者や家族ら15人ほどが集まって発足しました。
……
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。




