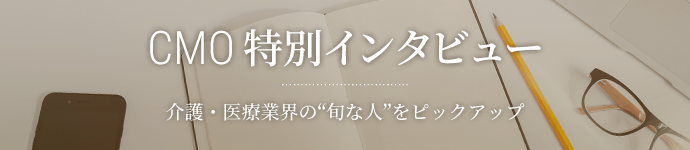
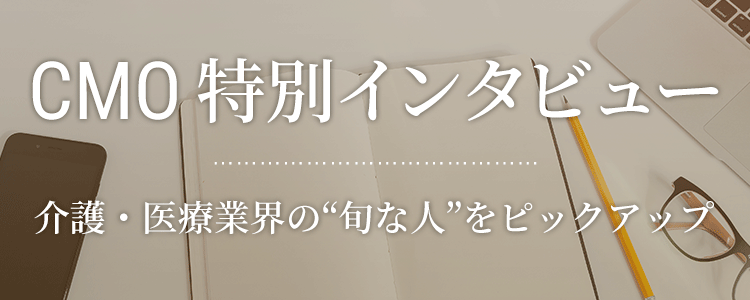
CMO特別インタビュー
※この記事は 2018年1月31日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
AIでケアマネジメントは進化する/岡本茂雄(株式会社シーディーアイ 代表取締役社長)【前編】
- 2018/01/31 09:00 配信
- CMO特別インタビュー
-


ケアプランの作成にAI(人工知能)を活用した実証プロジェクトが昨年11月、愛知県豊橋市で始まった。2009年度から8年分、およそ10万件にも上る介護保険のデータをAIに学習させ、同市内のケアマネジャーの協力を得ながら、約200人のケアプランを作るという日本初の試みだ。このプロジェクトを進めるシーディーアイ(東京都中央区)の岡本茂雄社長は、「AIと連携することで、ケアマネジメントは進化する」と強調する。岡本社長に話を聞いた。
「AI×介護」の可能性を語る岡本社長
―介護分野におけるAIの可能性について、どのようにお考えですか。
自動運転の世界では、AIを活用した技術開発が進んでいます。タクシーのように、乗り降りの要素が加わると話は別ですが、ただ目的地まで移動するという意味においては、人間の代わりの機能を果たしつつあります。
でも、介護は自動車の運転
……
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。




